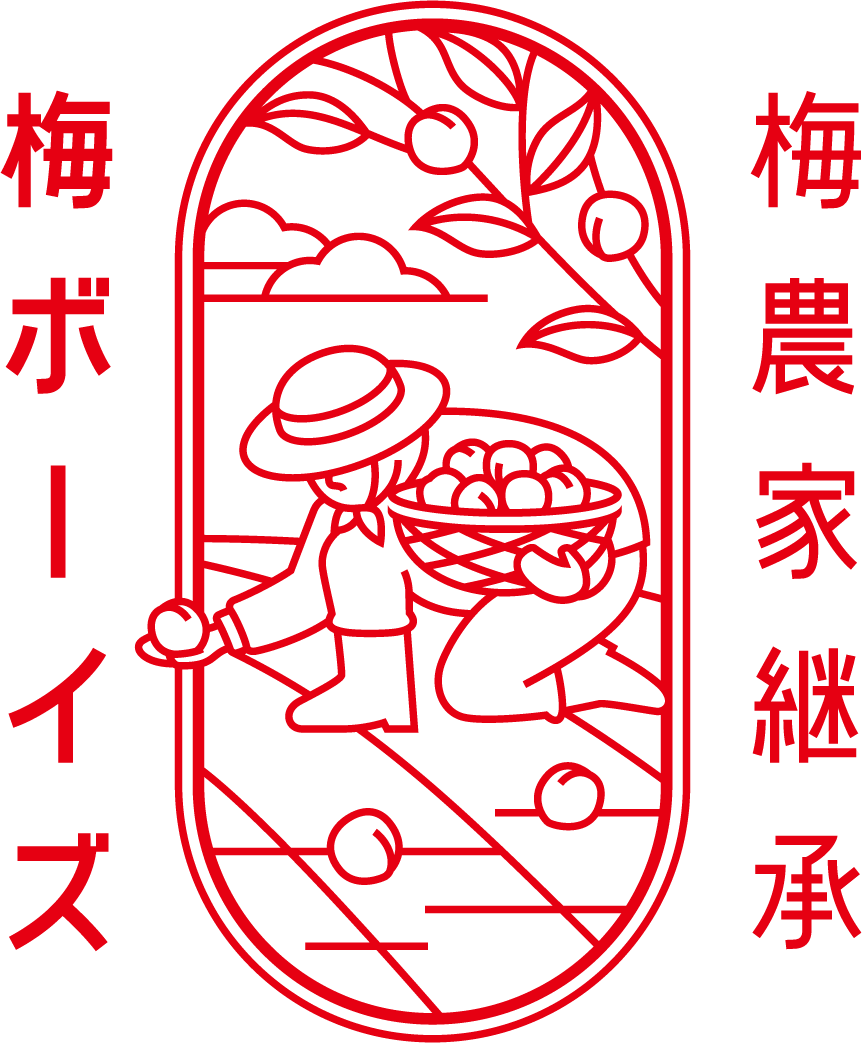梅干しの歴史|発祥国や名前の由来を解説。

日本では遣唐士とともに中国から持ち込まれ、そこから現代に至るまで日本の食文化として愛され続けています。
そこで、この記事では梅干しの名前の由来から、発祥国の中国、日本での梅干しの歴史について解説して行きます。
「梅干し」の名前の由来
梅干しの「干し」という言葉は、乾燥させるという意味です。
梅を塩漬けにした後、天日で干すことによって水分を抜き、保存性を高めるこの方法が、「梅干し」という名称に反映されています。
また、梅を塩漬けにすることで発酵を防ぎ、梅特有の酸味と塩味が強調されることから、特有の風味が生まれます。
梅干しの発祥国は中国
梅干しの発祥とされる国は2000年前の中国です。中国では紀元前から梅が栽培されており、梅を利用した食品や薬としての使用が古くからありました。
梅干しの原型とも言える梅の保存法は、古代中国で発達したとされ、それが日本に伝わり、独自の発展を遂げたと考えられています。
中国では、梅を塩漬けにし、発酵させることで「酸梅(すあんばい)」という食品を作っており、これが梅干しの原形であるとも言われています。
日本での梅干しの歴史

日本への到来
梅は中国原産であり、紀元前から栽培されていたとされます。梅干しの原型とも言える保存食は、中国から日本に伝わったと考えられています。
日本へは奈良時代に仏教とともに伝来したとされ、以降、日本独自の食文化として発展を遂げていきました。
平安時代
平安時代には、梅干しは主に貴族の間で珍重され、食用だけでなく、薬用としても利用されていました。
この時代には、すでに梅を塩漬けにして保存する方法が確立されており、健康維持や疾病予防のために用いられていたとされます。
戦国時代
戦国時代には、梅干しは武士たちの間で重宝されるようになりました。長期間の保存が可能であり、また、エネルギー源としても優れていることから、長期の軍陣や遠征時の携帯食として活用されました。
さらに、疲労回復や健康維持の効果もあるため、戦場での必需品とされていたと伝えられています。
江戸時代
江戸時代に入ると、梅干しは一般の民衆の間でも広く食されるようになります。この時代には、梅の大量生産と流通が始まり、梅干しは日本人の食生活に欠かせない食品の一つとなりました。
特に、保存食としての価値が高く評価され、飢饉時の備蓄食としても利用されていたことが記録されています。また、江戸時代には様々な味付けの梅干しが登場し始め、現代につながる梅干しの多様性の基礎が築かれました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?梅干しは、2000年前の中国から生まれた食品です。それが日本に渡り、現代に至るまで愛され続けています。
そんな梅干しの歴史を知ることで、より梅干しの楽しみが増えたのではないでしょうか?